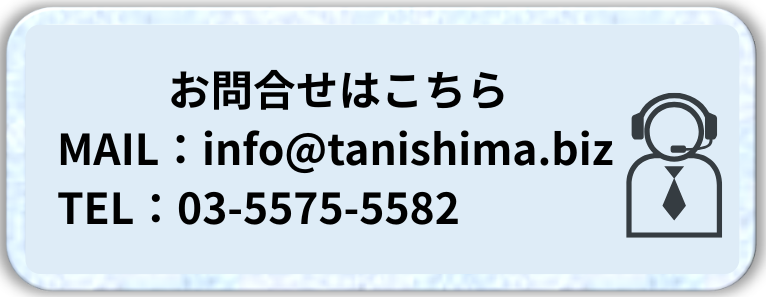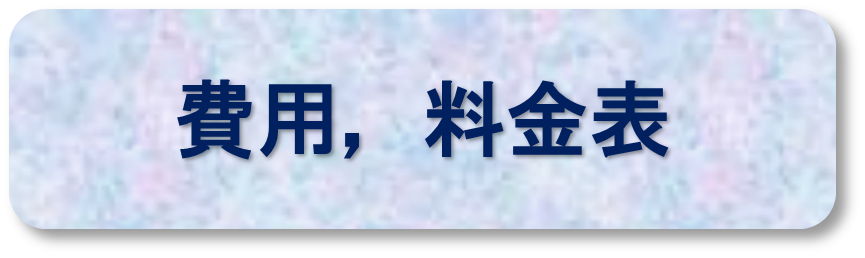「基本契約書がないまま、注文書と請書だけで取引している」
「元請の指示で、契約書を交わす前に工事を始めてしまった」
もし、このような慣行に心当たりがあれば、貴社は建設業法違反のリスクを抱えているかもしれません。
国土交通省が公表している「建設業法令遵守ガイドライン」では、建設工事の契約に関して、数多くの違反事例が指摘されています。知らなかったでは済まされないこれらのルールは、建設業者を不当な契約から守ると同時に、遵守すべき義務を課すものです。
本ページでは、建設業法務を専門とする行政書士が、ガイドラインを基に、特に問題となりやすい下請契約や注文書・請書の取り扱いに焦点を当て、処分リスクを回避するための具体的なポイントを解説します。
なぜ契約方法が厳しく定められているのか?
建設工事は、その性質上、追加工事や仕様変更が発生しやすく、代金の支払いをめぐるトラブルも少なくありません。特に元請負人と下請負人の間では、立場の違いから下請負人が不利な状況に置かれがちです。
そのため建設業法では、契約内容を事前に書面で明確化することを徹底させ、当事者間のトラブルを未然に防ぎ、公正な取引関係を確保することを目的としています。口約束や曖昧な書面での契約は、この目的に反するため、厳しく規制されています。
適法な契約締結方法は、主に以下の三類型が想定されております。
①個別契約書
②基本契約書+注文書・請書の交換
③注文書・請書の交換のみ+約款
| 建設業法令遵守ガイドライン(第11版)
①工事毎の個別契約による場合個別契約書には、法第19条第1項各号(前頁の14項目)に掲げる事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付して下さい。 ②当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合 ③注文書及び請書のそれぞれに、あらかじめ同意した内容の基本契約約款を添付又は印刷する場合 |
ガイドラインが示す「建設業法違反となる4つの契約事例」
「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)」では、以下のような行為が建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)に違反する可能性があると明示されています。
事例①:書面による契約を行わなかった
最も基本的な違反です。請負金額の大小や工事期間の長短にかかわらず、すべての建設工事で書面による契約が義務付けられています。 口約束のみで工事を受発注することは法律違反です。
事例②:契約書の記載事項が不足している
契約書を交わしていても、建設業法第19条が定める15の必須記載事項が漏れていれば違反となります。
この点、下請から通報され、行政指導や行政処分を受けることがあります。下請とのトラブルが発端ですが、主に次のような契約上の問題が原因となっております。
1. 支払い条件の食い違い
2. 施工のやり直しをさせられる
3. 工期など条件の一方的な変更
4. 不可抗力による損害負担など
請負契約書の法定記載事項は次の解説ページをご覧ください。
⇒関連解説ページ:【行政書士顧問事例】建設業法に基づく注文書・請書と15の必須記載事項
事例③:契約前に工事に着手させた
「とりあえず着工して、書類は後で」という慣行は、典型的な違反事例です。契約は工事に着手する前に、当事者双方が署名または記名押印した書面を相互に交付し、完了させなければなりません。工事の途中や完了後に契約書を作成・交付しても、法律の要件を満たしたことにはなりません。
事例④:注文書・請書のみで、契約約款がない
継続的な取引がある場合、「基本契約書」を締結し、個別の工事は「注文書」「請書」で行うことが一般的です。しかし、この基本契約書を締結していなかったり、注文書・請書に契約約款を添付・印刷していなかったりする場合は、記載事項を満たさない不完全な契約とみなされ、違反となる可能性があります。
【最重要ポイント】注文書・請書だけで契約する場合の絶対条件
ガイドラインでは、注文書と請書の交換のみで契約を締結する場合のルールを明確に定めています。
【ガイドラインからの要点】
注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。
これは、注文書と請書だけでは、建設業法が求める15の必須記載事項をすべて網羅することが難しいためです。
注文者(元請)が渡す注文書と、請負人(下請)が返す請書の両方に、全く同じ契約約款(15項目を満たす詳細な条件が書かれたもの)が添付または裏面に印刷されている必要があります。これにより、双方が同一の契約条件に合意したことが明確になります。
注文書にしか約款が添付されていない、あるいは約款の内容が双方で異なるといったケースは、適法な契約とは認められません。
法令遵守でリスクを回避し、健全な経営を
建設業法における契約ルールは、手続きが煩雑に感じられるかもしれません。しかし、これらはすべて、事業者自身を不測のトラブルから守るための重要なセーフティネットです。
「うちは大丈夫」と思っていても、法令の解釈は年々厳格化しています。一度監督処分を受ければ、企業の信用失墜は避けられません。
谷島行政書士法人グループでは、最新の「建設業法令遵守ガイドライン」に基づき、貴社の契約実務が法的に問題ないか診断するリーガルチェックや、実態に即した各種契約書(基本契約書、注文書・請書)の作成をサポートしています。
法令遵守体制を強化し、安心して事業に専念するために、ぜひ一度、当事務所の専門家にご相談ください。
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】
コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】