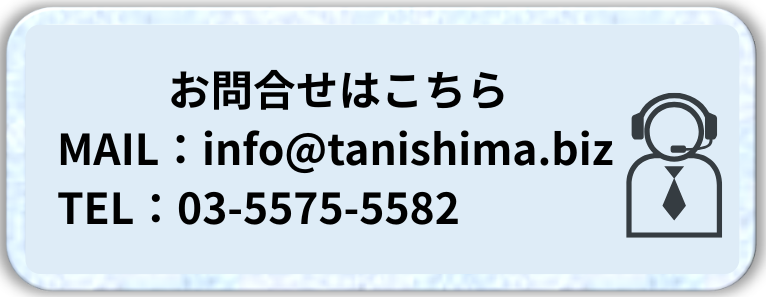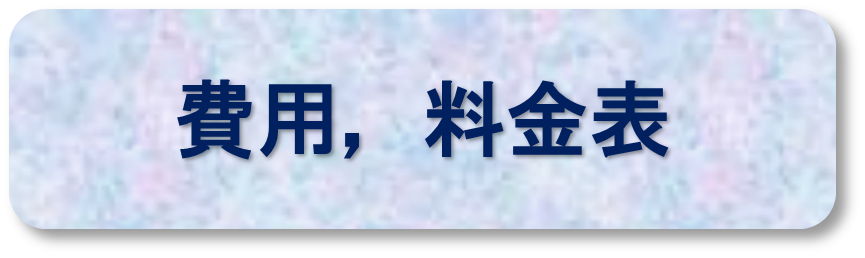内容
1級技士補の監理技術者補佐になりやすい指定建設業・技術検定業種等の対応
1級技士補の監理技術者補佐になりにくい(直接の技術検定無し)許可業種の対応
現場専任の兼務が認められる専任特例2号と監理技術者補佐
建設業法で一定の建築物の工事現場では、主任技術者または監理技術者証をもつ監理技術者が専任しなければならない義務が定められています。
実務上の柔軟性や技術者不足の状況に対応するために特例的に兼務が認められるケースも存在します。それが専任特例2号と、監理技術者補佐の制度です。
ここでは建設業法改正で専任特例1号とともに法整備された「専任特例2号」について説明します。
そもそも専任現場となる工事とは
建設業法で、請負金額が4,500万円以上の工事現場には、専任現場とすべき義務があります。
この点、共同住宅は対象となりますが、長屋など専用住宅に近い建築制限の建物の場合、専任現場となることはありません。
4,500万円以上の請負工事であればすべてが該当するものではないのです。
そのような専任が必要な条件に当てはまらない用途であれば、主任技術者は、複数の現場を掛け持ち(兼務)することが可能です。例えば数千万円規模以下の工事であれば、1人の主任技術者が時間帯を調整しながら2つ以上の現場を担当することも法律上は許容されています。
ただし、あくまで各現場で誠実に職務を全うできる範囲に限るとされています。無理のある兼務で施工管理が疎かになれば問題となるため、兼務可能とはいえ慎重な判断が必要です。
専任特例2号(特例監理技術者)による兼務
専任義務のある規模の工事現場でも、ある条件を満たせば1人の監理技術者が2つの現場を兼務できる特例制度があります。これを専任特例2号といい、法改正以前は特例監理技術者制度とされておりました。
具体的には、監理技術者が一人でも、兼務したい現場に「監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)」を専任で配置するなどを条件に、1人の監理技術者が最大2現場まで担当可能となる制度です。
監理技術者補佐とは
非常に便利な特例ですが、監理技術者補佐になるには、以下の要件を満たす者となります。
1. 主任技術者になれる資格を有する者で、一級の技術検定第一次検定合格者(いわゆる1級施工管理技士補)など一定の要件を満たす人
2. その他、特定建設業許可の営業所専任技術者になれる者
1級技士補の監理技術者補佐になりやすい指定建設業・技術検定業種等の対応
上記1は、一級施工管理技士一次試験合格者、つまり「技士補」が必要となります。したがって、施工管理技士が整備されている、業種では十分可能性があります。例えば、指定建設業は多くが技術検定を有しております。
- 指定建設業
一 土木工事業
二 建築工事業
三 電気工事業
四 管工事業
五 (鋼構造物工事業は施工管理技士無し)
六 (舗装工事業は施工管理技士無し)
七 造園工事業
さらに、指定建設業等でなくても、以下の「電気通信工事施工管理技士」のような技術検定が整備されている場合は、一次試験合格で十分可能です。
| 建設業法施行令
(技術検定の検定種目等) 第三十七条 法第二十七条第一項の規定による技術検定(以下「技術検定」という。)は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目(以下「検定種目」という。)に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。 |
|
| 検定種目 | 検定技術 |
| 建設機械施工管理 | 建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 土木施工管理 | 土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 建築施工管理 | 建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 電気工事施工管理 | 電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 管工事施工管理 | 管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 電気通信工事施工管理 | 電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
| 造園施工管理 | 造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
1級技士補の監理技術者補佐になりにくい(直接の技術検定無し)許可業種の対応
上記1は、一級施工管理技士一次試験合格者、つまり「技士補」が該当する業種でない施工管理技士しか存在しない「機械器具設置工事」などの業種では、技士補の制度を使うことはできません。
ただし、他の業種の一級技士補は、当該業種を資格のみで監理技術者となれませんが、指定建設業7業種以外なら、実務経験ルートがあります(建設業法15条2号ロ該当)。
実務経験ルートとして、一級技士補または二級技士補は合格後、指定学科相当としての3,5年で足りるとされる実務経験短縮はできます(令和5年改正の建設業法7条2号ハ)。それに指導監督的実務経験2年があれば、監理技術者となりえます。
そうすると、上記2の建設業法15条2号ロ該当者となり、監理技術者証がなくても監理技術者補佐となれるということです。
したがって、指定建設業7業種以外であれば、指導監督的実務経験で監理技術者証をとることも有用です。
専任特例2号の監理技術者補佐らは監理技術者証が不要
監理技術者補佐らを統括する、専任の監理技術者は監理技術者証が必要です。しかし、監理技術者証が必要なわけではありません。この点、指導監督的実務経験の立証方法は、各都道府県や国土交通大臣等の許可行政庁と、監理技術者証発行団体(CE財団)で大きく異なります。
したがって、監理技術者証が交付されない、つまり立証資料が残っていない技術者でも、実態があれば許可行政庁では認められることもあります。
そうすることで、監理技術者兼務に必要な建設業法15条2号の該当性を満たせる「監理技術者証をもたない監理技術者補佐」が活躍できることになります。
| 建設業法
(許可の基準) 第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。 二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。 イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
営業所専任技術者を監理技術者補佐に配置転換すること
営業所専任技術者でも監理技術者証は必須ではありません。東京都などでは指導監督的実務経験の立証資料が不要になるという利点にすぎません。
したがって、(指導監督的実務経験があっても立証が大変である)営業所専任技術者になっている方は、監理技術者証を持っていなくても、すぐに監理技術者補佐に配置転換することで、監理技術者補佐を確保できる可能性があります。
つまり、監理技術者補佐を増やす場合、営業所専任技術者になれる候補者を多く確保することで、営業所専任技術者と専任現場の監理技術者補佐のどちらにもなれる技術者を確保することが出来ます。
専任特例1号との違いは主任技術者の兼務不可であること
特例1号では連絡員が必要です。一方で、特例2号では監理技術者補佐が必要になります。
監理技術者補佐というからには、主任技術者の専任に使えません。したがって、現場監督が豊富な企業には、主任技術者が多いため、問題にならないかもしれません。
一方で、主任技術者が少ない建設業者では、特例1号を使うべきか検討すべきです。双方、要件が異なるため、貴重な監理技術者
監理技術者として兼務する場合でも最終的な責任はその監理技術者本人にあり、補佐する者はあくまで指揮下で補助する立場という点は変わりません。
工期上の現場専任の例外
工事の進捗状況によっては、一時的に専任でなくても差し支えない期間があります。例えば「工事着手前の準備期間」や「工事完了後の書類整理のみ残っている期間」、「工事を全面中断している期間」など、現場が実質的に動いていない期間で。こうした場合には、一時的に現場を離れて他業務を行っても専任義務違反には問われません。これらは厳密には兼務の例外というより「専任すべき期間」の例外ですが、実務上知っておきたいポイントです。
専任特例2号と監理技術者補佐のまとめ
以上の専任特例2号と監理技術者補佐により、一定の条件下では監理技術者証が必要な専任現場であっても、兼務が認められるような合理化特例が建設業法改正で実現しております。
ただし、特例であるため、制度の理解を得たうえで適用すべきものです。そうでないと、専任義務違反となってしまいます。
複雑な点があれば、顧問行政書士や谷島行政書士法人にご相談ください。
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
▶ 行政対応・顧問
▶ TAKUMIジョブ(外国籍人材紹介)
▶ 外国人登録支援機関業務
▶ TAKUMI人事
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】
コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは