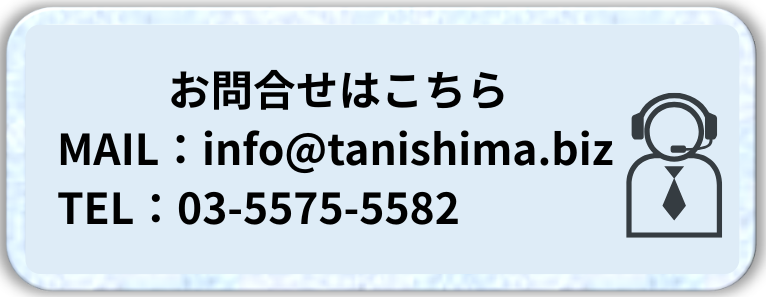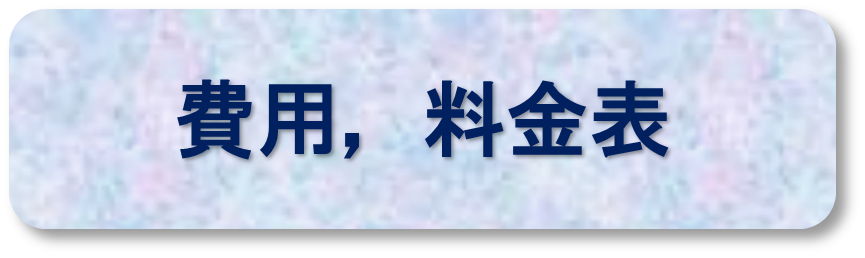建設業の工事現場では、適切な施工管理のために主任技術者または監理技術者という「配置技術者」を置く義務があります。
特に大規模な下請額の工事では、より高度な「監理技術者」を配置し、その監理技術者は原則としてその現場に専任で従事しなければなりません。さらに監理技術者証が必要な専任現場とは別の基準であり、複雑です。
本記事では、建設業法に基づく監理技術者の定義や「専任」を要する工事現場の要件、そして例外ケースや主任技術者との違いについて詳しく解説します。
内容
監理技術者証とは何か?その役割と携帯義務
まず監理技術者資格者証(通称:監理技術者証)とは、ある技術者が特定の建設工事で監理技術者としての資格・要件を満たしていることを示すカード型の証明書です。
これは国土交通大臣指定の交付機関である「一般財団法人 建設業技術者センター」に申請し、所定の資格や実務経験を満たす技術者に交付されます。
監理技術者証が必要となるのは、工事現場にその技術者を監理技術者として専任で配置する場合です。
建設業法上、監理技術者として現場に専任で従事する人は監理技術者資格者証の交付を受けていなければならず、さらに定期的に監理技術者講習を修了している必要があります。
現場ではこの資格者証を携帯し、発注者(注文者)から請求があれば提示しなければならないと規定されています。つまり、一定規模以上の工事現場で監理技術者を務めるには監理技術者証の保持が必須となるわけです。
監理技術者と監理技術者証が必要な工事現場の要件
監理技術者証が必要になる場面を理解するには、どのような工事に監理技術者の配置が義務付けられるかを知る必要があります。建設業法第26条では、発注者から直接工事を請け負う元請業者が特定建設業許可を受けている場合で、なおかつその工事で締結する下請契約の合計金額が一定以上になるとき、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければならないと規定しています。
その「一定の金額」とは具体的に5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)です。
| 元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。 |
出典:CE財団、https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html
つまり、元請の特定建設業者が下請けに出す金額の総額が5,000万円(建築一式では8,000万円)を超えるような大規模工事では、現場に主任技術者ではなく監理技術者を配置することが必須となります。
この条件に該当する工事では、もはや主任技術者では不十分で、より高度な資格・経験を持つ監理技術者を置く必要があるということです。
専用住宅や併用住宅の一部(住宅床面積2分の1以下など)を除き、なお公共工事や大型商業施設などの民間工事問わず、上記金額規模に達する工事では監理技術者の配置が必須となります。
以上をまとめると、監理技術者証が必要な工事現場とは、以下を指します。
1. 「発注者から直接請け負った工事で下請総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)ゆえに監理技術者の配置が必要な現場
2. 1に加え、多数の者が利用する等の用途が一定範囲の請負金額4,500万円(建築一式9,000万円)以上となる監理技術者等の専任が義務付けられる現場
このような現場では監理技術者証を持った有資格者を配置しないと法律違反となるため、注意が必要です。
専任を要する工事現場とは?現場専任の義務と条件
次に、「専任」を要する現場について解説します。監理技術者を配置すべき工事では、その監理技術者(または主任技術者)は原則として当該工事現場に専任で配置されなければなりません。
建設業法施行令第27条では、監理技術者等を専任で配置すべき工事の条件が定められています。その条件は大きく用途面で「公共性のある施設・工作物」または「多数の者が利用する施設・工作物」に関する重要な建設工事であること(個人住宅や長屋など一般の戸建住宅を除く)とされております。
例えば、学校・病院・マンション・商業施設・道路・橋梁といった不特定多数が利用する建築物やインフラの工事で、請負金額が4,500万円(建築一式9,000万円)以上のものはこの専任配置の対象になります。
逆に、個人の住宅や小規模な長屋などは公共性が低いため、この「重要な建設工事」には該当しません。
専任の誤解:常駐でなく短期間現場を離れること
この現場専任の義務は、工事の安全かつ適正な施工を確保するために設けられた規定で、一般に「現場常駐」と呼ばれることもあります。
このように、「専任」と聞くと「必ず常に現場に居なければならない(常駐)」と誤解されがちですが、必ずしも終日現場に貼りつくことを要求するものではありません。
建設業法上は、技術者が研修・講習の受講や休暇取得など合理的な理由で短期間現場を離れることは認められています。
その場合、資格を有する代理の技術者を配置したり常時連絡が取れる体制を整えるなど、適切な施工管理が必要となります。また発注者や元請けの了解を得ていることも求められます。
| ① 適切な施⼯ができる体制を確保(必要な資格を有する代理の技術者の配置、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制の確保等)し、
② その体制について、発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば、差し支えありません。 |
このように、法律上の「専任」とは他現場との掛け持ち禁止という意味であり、一時的な不在まで厳しく禁じているわけではない点に注意が必要です。
まとめると、専任を要する現場とは「重要な公共性のある工事で、請負金額が4,500万円(建築一式9,000万円)以上の現場」を指し、そこでは監理技術者(または主任技術者)は他の工事を兼務せず当該現場の職務に専念する義務があります。
主任技術者の専任や、監理技術者の兼務でよい工事現場とは
以上から、請負金額5,000万円の住宅工事の場合でも状況によって以下の通り、結論が異なります。
1. 共同住宅で、下請額3,000万円なら、主任技術者の専任
2. 専用住宅で、下請額5,000万円なら、監理技術者の兼務
まとめと顧問行政書士への相談
監理技術者証が必要な専任現場とは、特定建設業者が受注した下請額5,000万円以上であることで監理技術者の配置が義務付けられ、4,500万円以上の請負額の工事であることで現場に専任で監理技術者を置かなければならない工事現場です(建設業法26条各項)。
監理技術者として現場に専任するためには、監理技術者資格者証の交付を受け監理技術者講習を修了していることが条件となります。
専任義務のある現場では原則一現場に一人の技術者が張り付き、他現場を兼ねることはできませんが、専任特例1号や2号(特例監理技術者制度)など一定の例外も存在します。
抱える監理技術者証を有する監理技術者と、主任技術者の配置も踏まえ、自社の工事にどの技術者が必要かを正しく把握することが、施工体制の適正化と法令遵守につながります。
監理技術者証の要否や専任義務の判断に迷う場合は、顧問行政書士に相談し、適切な対応を図りましょう。
谷島行政書士法人では、人材配置計画の策定から帳簿対応まで幅広く対応可能です。建設業法のことならなんでもご相談ください。
参考文献・法令: 建設業法第26条、第27条、国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」等
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
▶ 行政対応・顧問
▶ TAKUMIジョブ(外国籍人材紹介)
▶ 外国人登録支援機関業務
▶ TAKUMI人事
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】
コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは