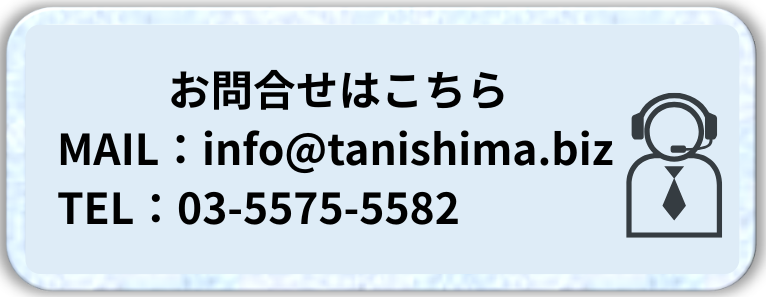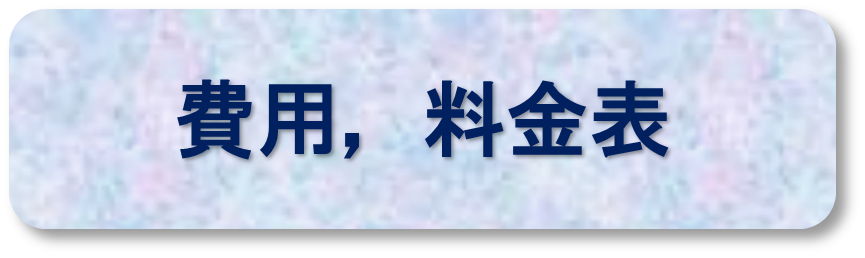内容
Q1. 建設業法第19条の「十六 その他国土交通省令で定める事項」とは何ですか?
Q2. 建設リサイクル法に関する条項も入れた方がよいですか?
Q3. 違約金(遅延損害金)の条項は必ず記載しなければなりませんか?
Q4. 違約金の率(例:1000分の1)に法的な上限はありますか?
Q5. 事業者間の契約でも、遅延損害金の利率に上限があるのではないでしょうか?利息制限法は適用されませんか?
注文書・請書の交換のみで契約してよい?
建設工事の現場では、「言った・言わない」のトラブルが後を絶ちません。こうしたトラブルを防ぎ、当事者双方の権利を守るために、建設業法では書面による契約締結を義務付けています。
たとえ「注文書」と「請書」のやり取りのみであっても、それは法的に有効な契約です。しかし、建設業法で定められた約款を添付していない場合や、していてもその必須の項目が記載されていなければ、法令違反となります。
⇒関連解説ページ:建設業法違反で処分も?契約書・注文書で失敗しないための法令遵守ガイド
本ページでは、建設業法令を専門とする行政書士が顧問として相談対応する形式をとり、建設業法で定められた契約書の記載事項や、実務でよくある疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
なぜ建設工事では「書面契約」が義務なのか?
口約束だけでも契約は成立しますが、建設工事は金額が大きく、内容も複雑になりがちです。そのため、当事者間の認識のズレからトラブルに発展しやすくなります。
そこで建設業法第19条では、請負金額の大小にかかわらず、すべての建設工事で15の事項を記載した書面を交付することを義務付けています。これは、契約内容を明確にすることで、不当に不利な契約から事業者を保護し、紛争を未然に防ぐことを目的としています。
この義務を怠ると、建設業法違反として監督処分の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
建設業法第19条が定める「15の必須記載事項」
契約書や注文書・請書には、以下の15項目を必ず記載しなければなりません。
- 工事内容
- 工事名、工事場所、設計図面や仕様書など、工事の内容が特定できるように記載します。
- 請負代金の額
- 消費税を含めた総額を明確に記載します。単価契約の場合は、その計算方法を示します。
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工期の始期と終期それぞれを「〇年〇月〇日」のように、具体的な日付を記載します。
- 工事を施工しない日又は時間帯
- 週休2日制の導入など、工事をしない日や時間帯について取り決める場合に記載します。
- 前金払・出来高払の定め
- 前払金や、工事の進捗に応じて支払う「出来高払い」を行う場合に、その支払時期と方法を記載します。
- 設計変更・工事中止の場合の取扱い
- 当事者の一方から設計変更や工事中止の申し出があった場合の、工期や代金の変更、損害の負担について定めます。
- 不可抗力による損害負担
- 台風や地震など、当事者の誰も悪くない理由(不可抗力)で損害が出た場合の負担について定めます。
- 価格変動に基づく代金変更
- 急激なインフレなど、経済情勢の変動によって資材価格が高騰した場合の代金変更について定めます。
- 第三者損害の賠償負担
- 工事中に通行人などに損害を与えてしまった場合の、損害賠償の負担について定めます。
- 支給資材・貸与機械
- 注文者が資材を提供したり、建設機械を貸したりする場合に、その内容や方法を定めます。
- 検査及び引渡しの時期
- 工事完成後、注文者が完成を確認するための検査の時期・方法と、目的物の引渡しの時期を定めます。
- 完成後の代金支払時期
- 引渡しを受けた後、注文者が請負代金を支払う時期と方法を定めます。
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 完成した建物に欠陥など(契約不適合)があった場合の、修補などの責任について定めます。保証保険契約を締結する場合はその内容も記載します。
- 履行遅滞・違約金
- 工期の遅れや代金の支払遅延など、契約違反があった場合の遅延利息や違約金について定めます。
- 紛争の解決方法
- 当事者間でトラブルが解決しない場合の解決手段(例:建設工事紛争審査会、裁判所など)を定めます。
本来は上記項目が請負契約書の記載として想定されております。したがって、契約書作成と締結が望ましいです。しかし注文書・請書の交換のみであっても、上記の約款を添付することが重要です。
| 建設業法令遵守ガイドライン(第11版)
イ 注文書及び請書の交換のみによる場合 ① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。 |
出典:国土交通省、https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001765310.pdf
-建設業法に基づく法定記載事項
| 建設業法
略 (建設工事の請負契約の内容) 第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 工事内容 二 請負代金の額 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め 九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 十五 契約に関する紛争の解決方法 十六 その他国土交通省令で定める事項 |
注文書・請書に関するQ&A
ここでは、お客様からよく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 建設業法第19条の「十六 その他国土交通省令で定める事項」とは何ですか?
A1. これは、将来的に法律を改正することなく、省令によって柔軟に記載事項を追加できるようにするための、いわば「空き番号」のような規定です。2024年現在、この規定に基づいて省令で定められている事項はありません。 したがって、契約書作成にあたっては、上記の15項目を網羅していれば問題ありません。
Q2. 建設リサイクル法に関する条項も入れた方がよいですか?
A2. はい、対象となる工事の場合は記載が義務付けられています。
解体工事や新築工事などで、床面積の合計が一定規模以上になる「対象建設工事」の場合、建設リサイクル法に基づき、以下の4項目を契約書に記載する必要があります。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化施設の名称・所在地
- 再資源化に要する費用
また、近年はコンプライアンスの観点から「反社会的勢力の排除に関する条項」を盛り込むことが一般的です。
Q3. 違約金(遅延損害金)の条項は必ず記載しなければなりませんか?
A3. 違約金を定めること自体は任意です。しかし、もし違約金について取り決めをするのであれば、その内容を契約書に記載する義務があります(建設業法第19条第1項第14号)。
これは「損害賠償額の予定」といい、実際の損害額を証明する手間なく、契約内容に基づいて請求できるメリットがあります。後のトラブルを防ぐためにも、明確に定めておくことを強く推奨します。
Q4. 違約金の率(例:1000分の1)に法的な上限はありますか?
A4. 事業者間の契約であれば、法律による上限はありません。
公共工事では年14.6%が標準ですが、民間工事では商慣習として「請負代金額の1日あたり1000分の1(年利換算36.5%)」という率が広く使われています。当事者双方が合意しているのであれば、この率で契約しても法的に問題ありません。
Q5. 事業者間の契約でも、遅延損害金の利率に上限があるのではないでしょうか?利息制限法は適用されませんか?
A5. いいえ、工事請負契約には利息制限法は適用されません。
利息制限法は、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)に適用される法律です。工事請負契約は「仕事の完成」を目的とする契約であり、お金の貸し借りではないため、適用対象外となります。
また、事業者と「消費者」の契約であれば消費者契約法(上限年14.6%)が適用されますが、事業者同士の契約には適用されません。
そのため、事業者間の契約においては、法律上の上限はなく「契約自由の原則」に基づき、当事者の合意が最優先されます。
注文書や請負契約書の作成とチェックは顧問行政書士がいれば万全
建設工事の契約書は、法律で定められた事項を網羅するだけでなく、個別の工事内容やリスクに応じた内容にすることが重要です。
安易に雛形を使い回すと、自社にとって不利な条項に気づかなかったり、いざという時に会社を守れなかったりする可能性があります。
谷島行政書士法人グループでは、建設業法務に精通した専門家が、貴社の実情に合わせた契約書の作成から、相手方から提示された契約書のリスク診断(リーガルチェック)まで、幅広くサポートいたします。
建設工事の契約に関するお悩みは、お気軽に当事務所までご相談ください。
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】
コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】