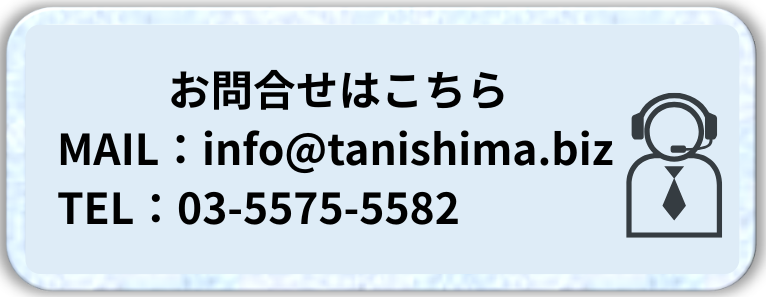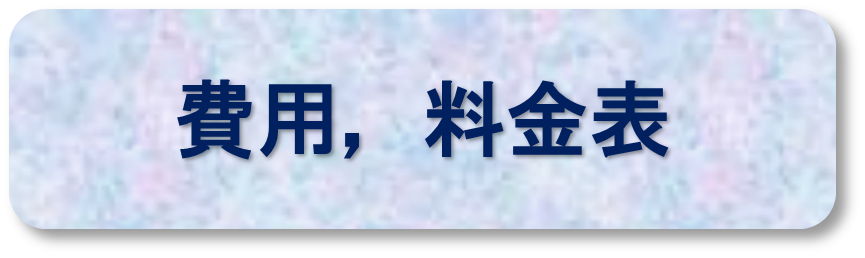内容
Q1. 解体工事業を新たに業種追加する際、専任技術者の「解体の実務経験」は、平成27年以降に資格を取得した場合は不要なのですか?
Q2. 建築施工管理技士や土木施工管理技士を持っている場合、解体工事施工技術講習は不要ですか? (例:令和2年合格等)
業種追加における専任技術者について
Q1. 解体工事業を新たに業種追加する際、専任技術者の「解体の実務経験」は、平成27年以降に資格を取得した場合は不要なのですか?
結論から申しますと、「解体工事業」の専任技術者として認められる資格を平成27年(2015年)以降に取得した場合でも、一定の要件を満たせば実務経験は不要となります。ただし、資格の種類や取得時期によって異なるため、国土交通省や東京都の建設業許可に関する公式情報を確認し、要件に合致しているかの確認が必要です。
そもそも、平成28年(2016年)6月1日に「解体工事業」が独立した業種として追加された際、それまでとび・土工・コンクリート工事業の範囲で行われていた解体工事が新たに独立扱いとなりました。そのため、資格の扱いも法改正以降に再整理され、所定の資格を取得している場合は実務経験を省略できる法令が整備されています。
ただし、資格を取得していても、業種追加で解体工事業の許可を取得する際に、「この資格が解体工事の専任技術者として要件適合するか」という要件は変わらず存在します。以下のような例外や注意点もあるため、要件を満たしているか十分にご確認ください。
- 資格試験に解体分野の試験内容が含まれているか
- 資格を取得した日が改正後か改正前か
- 許可を受ける法人や個人が行う業種との整合性
Q2. 建築施工管理技士や土木施工管理技士を持っている場合、解体工事施工技術講習は不要ですか? (例:令和2年合格等)
基本的には不要となるケースが多いです。
特に、「1級建築施工管理技士」や「1級土木施工管理技士」など、指定された国家資格を有している場合は、解体工事業の専任技術者としての要件を満たせるため、別途の解体講習を受講しなくても良い場合があります。ただし、こちらも令和2年(2020年)合格など取得時期や合格した試験区分により取り扱いが異なる可能性がありますので、必ず公式情報や専門家にご確認ください。
解体工事業の新規許可及び業種追加に必要な技術者資格等
- 平成28年(2016年)6月1日施行の建設業法改正により、新たに「解体工事業」が独立した業種となりました。
- それまでは「とび・土工・コンクリート工事業」の一部として扱われていた解体工事が明確に区分されたことにより、専任技術者や実務経験の扱いも大きく変化しました。
- 経営業務の管理責任者の設置
- 営業所専任技術者の設置(資格または実務経験)
- 財産的基礎の要件
- 誠実性要件・欠格要件の確認
このうち、もっとも変更点が大きいのが、専任技術者に求められる資格要件や実務経験です。
- 資格要件
1級・2級の建築施工管理技士や土木施工管理技士、その他指定された国家資格を持っている場合、解体工事業の専任技術者として認められます。
近年では、試験科目に解体工事に関する知識が組み込まれている資格も増え、実務経験なしでの申請が認められるケースが拡大しています。
- 実務経験要件
指定資格がない場合、所定の工事に係る実務経験(一般建設業許可の場合は原則10年だが、指定学科卒業なら3,5年で良い等の例外もあり)を積むことが必要です。平成27年(2015年)の改正法施行以降、経験年数や資格の要件が大きく変わっているため、どの期間どのような工事に携わったか、しっかり整理することが大切です。
解体工事業の専任技術者になれる資格と経過措置の一覧と詳細
解体工事業の専任技術者になれる要件は、同じ資格でも年度ごとに異なる経過措置があり、非常に複雑です。
例えば、1級は問題ありません。しかし、2級の施工管理技士は種別によって、異なります。また技能検定等も含め、非常に複雑なので表にまとめました。まとめた表は以下の通りです。
解体工事業の専任技術者になれる資格者と経過措置一覧表
| 解体工事業の専任技術者になれる資格者と経過措置一覧表 | |||||
| H28年度以後の合格者の解体工事施工技術講習 | H27年度以前の合格者の解体工事施工技術講習 | H28年度以後の合格者の実務経験 | H27年度以前の合格者の実務経験 | H16年度以前の合格者の実務経験 | |
| 一級土木施工管理技士 | 不要 | 実務経験なければ必要 | 不要 | 1年 | 1年 |
| 二級土木施工管理技士:土木 | 不要 | 実務経験なければ必要 | 不要 | 1年 | 1年 |
| 二級土木施工管理技士:鋼構造物塗装 | 不要 | 対象外 | 合格後5年 | 合格後5年 | 合格後5年 |
| 二級土木施工管理技士:薬液注入 | 不要 | 対象外 | 合格後5年 | 合格後5年 | 合格後5年 |
| 一級建築施工管理技士 | 不要 | 実務経験なければ必要 | 不要 | 1年 | 1年 |
| 二級建築施工管理技士:建築 | 不要 | 実務経験なければ必要 | 不要 | 1年 | 1年 |
| 二級建築施工管理技士:躯体 | 不要 | 実務経験なければ必要 | 不要 | 1年 | 1年 |
| 二級建築施工管理技士:仕上げ | 不要 | 対象外 | 合格後5年 | 合格後5年 | 合格後5年 |
| 技術士:建設「鋼構造物及びコンクリート」を除く | 必要 | 必要 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 技術士:建設「鋼構造物及びコンクリート」 | 必要 | 必要 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 解体工事施工技士 | 不要 | 対象外 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 技能検定:とび・とび工 | 不要 | 対象外 | 不要 | 3年 | 1年 |
| ©谷島行政書士法人 |
©谷島行政書士法人
以上の各資格の主な解説を以下の通りいたします。
1級建築施工管理技士
- 建築工事一式の管理技術者として認められる国家資格。
- 平成28年6月の「解体工事業」新設に際し、解体工事分野も含む管理技術が習得できる資格として指定。
- 資格取得日が改正後であれば、実務経験不要の扱いとなる場合が多い。
2級建築施工管理技士(建築・仕上げ等)
- 建築のうち解体工事に関連する施工管理が可能な国家資格。
- 1級と比べると軽微な工事の範囲が主ですが、建築関連の解体工事を管理できる能力として評価される。
- 区分(建築・仕上げ)によって要件が異なる場合があるため、解体工事の範囲に該当するか要確認。
1級土木施工管理技士
- 土木工事分野での管理技術を習得している国家資格。
- 建築だけでなく「工作物の解体」を含む土木構造物の解体工事にも対応できる能力があると判断される。
- 改正以降に取得していれば、同様に実務経験を省略できることが多い。
2級土木施工管理技士(土木)
- 1級と同様に土木工事の管理を担うが、2級の場合は種別に制限がある。
- 該当がない種別でも解体工事業の専任技術者として認められるケースがあるため、可能性があるか行政書士にチェックしてもらうこと。
- 改正前後で認定範囲が変わっている場合がある。
技術士(建設部門)
- 建設に関する高度な知識・技術を持つと国から認定された資格。
- 一定の専門分野(建設部門)を有していれば、解体工事にも対応可能な専門技術を有するとみなされる。
解体工事施工技術講習修了者
- 「とび・土工・コンクリート工事業」から独立した解体工事業に特化した講習。
- 当該講習を修了することで、解体工事業登録と、実務経験不足を補い専任技術者の要件を満たすケースがある。
- 1級や2級の施工管理技士資格を平成27年度以前に合格していた場合などに利用されやすい。
その他(指定学科卒業者・既存資格)
- 建築学科・土木学科等の指定学科を卒業している場合、実務経験年数の短縮などが認められることがある。
- 「建設機械施工技士」など、国土交通省の告示で専任技術者として認められている資格も存在する。
- 必ず国交省や都道府県の公式情報で対象資格かどうかを確認すること。
「とび・土工」からの「解体」分離、経過措置、講習と実務経験
平成28年6月1日の「解体工事業」新設に伴い、従来は「とび・土工・コンクリート工事業」で解体工事ができていた事業者はそれ以降できなくなるため、一定期間の経過措置(猶予期間)が設けられました。下記は一般的な内容の例示です。
- 経過措置の適用対象
- 法改正前(平成28年6月1日以前)から解体工事を継続して行っていた事業者:とび・土工・コンクリート工事業の許可を得ていた事業者が多く該当。
- 経過措置の期間
- 施行日(平成28年6月1日)から一定期間内(例:3年、5年など)に、新設された「解体工事業」の許可申請を行うことで、旧許可の実績を活用できる制度。
- 実際には地域や状況によって異なるため、都道府県の告示や国交省の最新情報を要確認。
- 専任技術者の要件緩和
- 経過措置期間内に申請すれば、解体工事に必要な実務経験年数が短縮・免除されたり、特定の講習修了をもって要件を代替したりできることがあった。
- ただし、この猶予期間が既に終了している場合も多い(都道府県によっては令和元年~令和3年頃に終了)。
- 既存許可の扱い
- 旧「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を持っていても、法改正後は「解体工事」の範囲が除外される扱いとなるため、解体工事業の業種追加や経過措置の利用が必須となった。
- 現在は経過措置期間が終了しているところが多いため、新規で「解体工事業」を業種追加する場合は、現行ルールでの要件(資格または実務経験)のみが適用されるのが一般的。
解体工事業の資格と経過措置の注意点
- 資格の有効性チェック
- 一見「建設関連の資格なら大丈夫」と思われがちですが、実際には解体工事分野に対応した試験科目や区分に該当しているかどうかが重要。
- 取得時期・合格年度の確認
- 法改正(平成28年6月1日)後に取得している場合は、実務経験不要で認められる資格も多い。
- 同じ資格名称でも、取得時期によって解体工事業の専任技術者に該当しないこともあるため注意。
- 経過措置が終了している場合
- 現在は経過措置が終了しているケースが大半であるため、「旧許可の名残で大丈夫」と思い込まないこと。
- 業種追加や新規許可の手続きでは、現行の基準で資格・実務経験を確認される。
解体講習(解体工事施工技術講習)とは
- 「解体工事施工技術講習」は、解体工事に特化した知識を修得するための講習です。
- 指定された国家資格を有していない場合、または解体工事経験が不足している場合に、講習修了によって専任技術者の要件を補うことができる場合があります。
- ただし、前述のように1級・2級建築施工管理技士や土木施工管理技士などを保有している方は、当該講習が不要となるケースもあります。
申請時の注意点
- 資格証明書・合格証明書の準備
令和2年や令和3年に資格を取得・合格された場合は、取得年月日や試験区分の証明書をしっかり準備しましょう。 - 実務経験証明の整理
過去の解体工事の実績や工事内容の写真、契約書、請求書などを保管・整理しておくと、実務経験を証明しやすくなります。 - 都道府県や国の最新情報の確認
東京都の場合は「東京都都市整備局」、国土交通省の場合は「国土交通省 建設業許可」関連ページ等を参照し、最新の制度変更や運用状況を都度確認してください。
まとめ:解体工事業許可業種追加の経験・資格等
- 解体工事業の専任技術者として業種追加をする場合、資格を保有しているか、または実務経験を積んでいるかにより要件が大きく異なります。
- 平成27年(2015年)や平成28年(2016年)の法改正以降、新設された解体工事業では、改正後の資格取得者は実務経験が不要となるケースも増えており、1級・2級建築施工管理技士や土木施工管理技士等の資格をお持ちの場合は、解体講習が通常不要です。
- ただし、資格区分や取得時期で取り扱いが変わる場合がありますので、必ず公式情報を参照したうえで、行政書士に相談されることをおすすめいたします。
谷島行政書士法人のサポート
谷島行政書士法人グループでは、建設業許可の業種追加手続きや専任技術者要件に関するご相談を承っております。
解体工事業の専任技術者として認められる資格は、取得年度・試験区分・実務経験の有無などによって細かく変わるうえ、経過措置も既に終了している場合があります。
解体工事業の新設後に複雑化した許可要件で以下のようなことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
- 専任技術者要件の確認
- 実務経験証明書類の整備サポート
- 既存資格による解体講習不要の有無の確認
- 都道府県・国土交通省への申請手続き代行
専門的なアドバイスとスムーズな手続きで、皆様の許可取得を支援いたします。
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
▶ 行政対応・顧問
▶ 外国籍人材紹介
▶ TAKUMIジョブ(外国人登録支援機関業務)
▶ TAKUMI人事
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】
コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは