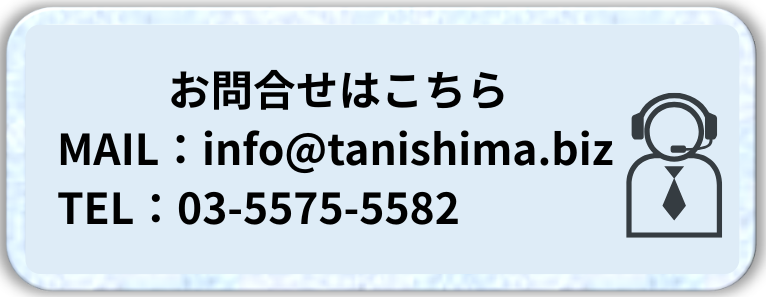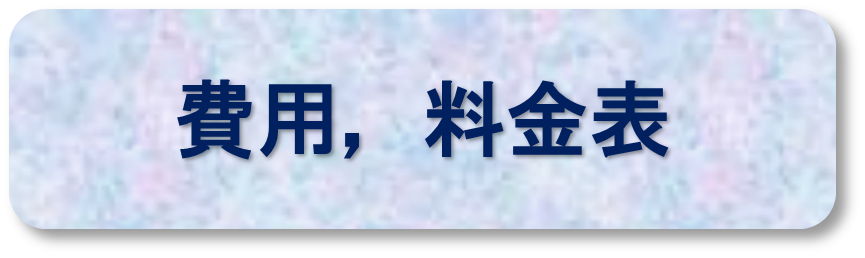内容
2.専任特例1号:9つの要件(建設業法施行規則第17条の2)
(1) 専任現場の場合、監理技術者証がある特定営業所専任技術者であること
(7) 連絡員を配置(建築一式、土木一式は同業種1年経験者)
はじめに:営業所専任技術者と監理技術者等の設置義務
建設業法は、営業所に専任技術者を置くことが許可要件です。これは専任であるため、現場と兼務できません。
さらに、工事現場の適正な施工を確保するため、許可業者はすべて、「主任技術者」や「監理技術者」を配置し、4,500万円以上の請負額では専任で置かなければならないケースを定めています。
ところが近年の法改正で、条件を満たす場合には営業所技術者(営業所専任技術者)と工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務できる特例制度として、専任特例1号の類似制度が拡充されました。技術者不足が深刻化する中で、合理的に人員を配置できるようにするためです。
本記事では、専任技術者が現場で監理技術者となれるのか、また類似する監理技術者等の「専任特例1号」とは何か、その要件はどうなっているのか、そして法改正により営業所専任技術者にも活用可能になった点などをわかりやすく解説します。建設業法施行規則第17条の2や新設された建設業法第26条の五を踏まえつつ、実際の運用に役立つポイントを紹介します。
1.営業所兼務に類似する監理技術者等の専任特例1号とは?
監理技術者等の専任特例1号とは、建設業法や関連法令が定める主任技術者・監理技術者の配置義務について、一定の要件を満たす場合は1人の技術者が複数現場を巡回しながら兼務できるようにする制度です。
本来、建設業法では規模の大きな工事(一定額以上の工事)については、主任技術者や監理技術者は「専任」で従事しなければならないとされています。いわゆる“現場専任義務”や“常駐義務”と呼ばれる規定です。しかし、特例1号に当てはまる工事であれば、あらかじめ定められた5つの要件をすべてクリアすることで、複数の工事現場を効率的に管理することが可能になります。
さらに近年の法改正では、営業所技術者(営業所専任技術者)がこの「特例1号」に類似の制度によって、工事現場の技術者(主任技術者・監理技術者)を兼務できる仕組みも新たに設けられました。これによって、営業所と工事現場が近距離であったり、ICTツールで状況を把握できたりすれば、営業所の業務と現場の技術管理を一人で行うことが可能になる場合があります。
2.専任特例1号:9つの要件(建設業法施行規則第17条の2)
では、具体的にはどのような条件を満たせば「営業所専任技術者の現場配置特例」を適用できるのか、建設業法施行規則第17条の2で定められた5つの要件を解説します。
(1) 専任現場の場合、監理技術者証がある特定営業所専任技術者であること
この要件は、営業所の専任技術者である場合、必須でない監理技術者証が必須となることになります。
なお、当然ですが、兼ねる専任現場は監理技術者証がある監理技術者である要件が必要です。
(2) 専任の営業所で締結した請負契約であること
この要件は、別の営業所の契約締結であれば、特例が使えないことを意味します。
(3) 兼ねる現場数は1つまで
この要件は、営業所の専任技術者が兼務できる現場数は無制限でなく、1つまでとなります。
営業所専任技術者は、2以上の現場数が禁止であり、非専任の現場も増やすことはできません。
(4) 1億円(建築一式は2億円)未満の請負金額
この要件は、金額が無制限の工事まで兼務できないことを意味します。
(5) 工事現場の距離と移動時間は概ね2時間以内
・同一の主任技術者または監理技術者が担当する工事現場同士の移動時間が「概ね2時間以内」であること
例:緊急事態(事故・労働災害など)発生時であっても、確実に速やかに現場に駆け付けられる範囲となります。
この要件は、距離・移動時間に関する制限です。2つ以上の工事現場を兼務する場合、それらの現場間は通常の勤務時間内で巡回可能な範囲でなければなりません。車両などによる移動で、具体的な目安として「おおむね2時間以内」という基準が提示されています。
(6) 下請契約は3次下請までの範囲
要点:
- 特例1号を適用する工事は、下請構造が1~3次下請契約までであること
- 4次、5次などさらに重層下請となった工事は後発的でも、それ以降は特例不可
この要件は、下請契約の重層構造が3次下請までに限られるという点です。建設工事には多くの下請業者が関わる場合がありますが、特例1号はある程度シンプルな下請体制しか持たない工事に限られます。
(7)連絡員を配置(建築一式、土木一式は同業種1年経験者)
要点:
- 主任技術者または監理技術者に代わって、工事現場に常駐して連絡をとる担当者を置くこと
- 土木一式・建築一式工事の場合、その連絡員は1年以上の実務経験を要する
この要件は、工事現場ごとに連絡員を配置することです。特例1号では技術者本人が常に現場にいるわけではないため、連絡員が不可欠となります。
特に土木一式工事や建築一式工事など規模の大きな仕事では、1年以上の実務経験を有する者でなければなりません。これにより、現場で起きる細かな問題に対応しやすくなっています。
(8) 施工体制をICTで確認
要点:
- 現場の状況をオンラインで随時確認できる措置を整備
- ビデオ会議システムや監視カメラ、建設キャリアアップシステムのAPIツールなどを活用
この要件は、情報通信技術(ICT)の活用です。特例1号で複数現場を巡回する際、移動のみで管理するのではなく、オンラインで状況を確認できる仕組みを整備する必要があります。具体的には、建設キャリアアップシステムとの連携ツールや現場Webカメラ、タブレットを使ったテレビ会議などが推奨されています。リアルタイムで作業員の出入りを把握したり、現場画像を確認したりできれば、遠隔で施工管理を補強できます。
(9) 人員配置計画書の作成・備え置き・保存
要点:
- 人員の配置計画に関する書類を作成し、現場に備え付けておく
- 記録として一定期間保管する義務
最後は、人員配置計画書をきちんと作成しておき、工事現場に備え付け、工事終了後も一定期間保存することが義務付けられています。誰がいつ現場に行き、どのような体制で管理するのかを明示することで、監理技術者・主任技術者が不在になり過ぎていないかなどをチェックできるようにする狙いがあります。
3.営業所技術者と専任現場又は非専任現場の兼務法令
2021年以降の建設業法改正により、新しく追加された条文が第26条の五です。ここでは、営業所技術者(いわゆる営業所専任技術者や特定営業所技術者)が工事現場の主任技術者・監理技術者と兼務できる仕組みが定められています。
建設業法(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
第26条の5
- 建設業者は、第26条第3項本文に規定する建設工事であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合、…(中略)…営業所技術者に主任技術者の職務を兼ねさせたり、特定営業所技術者に監理技術者の職務を兼ねさせることができる。
簡単に言えば、「専任する営業所」で締結した工事契約であり、かつ工事現場が営業所からの移動時間内でICT環境も整っていれば、営業所に常駐する技術者が実際に現場へも出向きながら主任技術者や監理技術者としての職務を兼務できます。要するに、営業所専任技術者と現場専任技術者の両方を一人が担うというイメージです。
これが実現できるようになった背景には、中小零細企業における人材不足という課題があります。特例1号によって、ある程度近い場所にある小規模工事なら、営業所での契約業務や事務処理も担当しつつ、必要なタイミングで現場を巡回する形でも法令違反にならないわけです。
4.活用時の注意点:兼務が認められないケース・留意点
特例1号はあくまで要件を満たした場合の例外措置です。以下の点に留意し、実務でトラブルにならないように注意しましょう。
- 工事規模や契約金額の上限
- 第26条の五では、請負代金額が一定金額未満の工事が対象となります。これは1億円未満であり、建築一式は2億円未満です。そのような大規模工事はそもそも適用外となり、現場専任が必須になる点を確認してください。
- 移動時間2時間以内という基準
- 2時間以内とされていても、実際の交通事情で往復にかなり時間がかかる地域は要注意。書面上2時間以内でも、実際に2時間を大幅に超えると問題視される恐れがあります。
- 情報通信技術の活用状況
- 必要とされるICT環境を整えていないと、特例の適用は認められません。通信用の回線、カメラやオンライン会議システムの導入など、具体的なツールの運用がポイントです。
- 事前の人員配置計画書作成と発注者への説明
- 特例を使う場合は、必ず書面で体制を明確化し、発注者から理解を得ることが望ましいでしょう。現場での監督員検査や立ち入り調査でも提示を求められる場合があります。
- 下請契約の段階が4次以上になる場合は適用外
- 自社では問題ないと思っていても、さらに下請けが下請けに出すとすぐに多重下請となるため、特例適用が崩れるケースがあります。契約段階ごとにしっかりチェックしましょう。
5.まとめ:特例を活用して効率的な技術者配置
監理技術者等の専任特例1号は、技術者不足への対応や交通・ICTの発達に合わせて設けられた制度です。複数現場の主任技術者・監理技術者を兼務する場合や、営業所技術者と現場の技術者を兼務する場合などに利用できるため、建設業界の人材配置を合理化できる可能性があります。
ただし、この特例はあくまで要件を満たした場合に限られ、すべての工事やどんな契約形態でも認められるわけではありません。特に、規模の大きな工事や下請構造が複雑な案件、現場が遠隔地にある案件では、法令上どうしても常駐の監理技術者や主任技術者が必要となります。
もし特例1号の活用を検討する場合は、
- 工事金額・下請構造の確認
- 現場間の移動時間と災害対応のシミュレーション
- ICT活用や連絡員の配置の具体策
- 発注者や監督官庁への事前説明
などをきちんと行い、法令適合性を確認したうえで導入しましょう。建設業法や国土交通省の解説資料、行政書士などの専門家に相談することもおすすめです。
本記事を参考に、監理技術者・主任技術者の特例を正しく理解していただき、企業の施工管理体制の向上にお役立てください。
以上が、監理技術者等の専任特例1号および営業所技術者との兼務に関する解説となります。改正条文(建設業法第26条の5)や施行規則(第17条の2)の要点を踏まえ、わかりやすい表現でまとめました。
さらに詳しい手続きや運用方法については、国土交通省のガイドラインや行政書士等の専門家にご相談ください。
監理技術者の専任技術者配置特例の法令、行政規則
本解説ページで参照した情報は以下の通りです。
監理技術者制度運用マニュアル:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
建設業法
| (営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
第二十六条の五 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。)又は第十五条(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。 一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。 二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。 三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。 四 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 2 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。 3 第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。 4 前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 |
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
▶ 行政対応・顧問
▶ 外国籍人材紹介
▶ 外国人登録支援機関業務
▶TAKUMI人事
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】
コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは