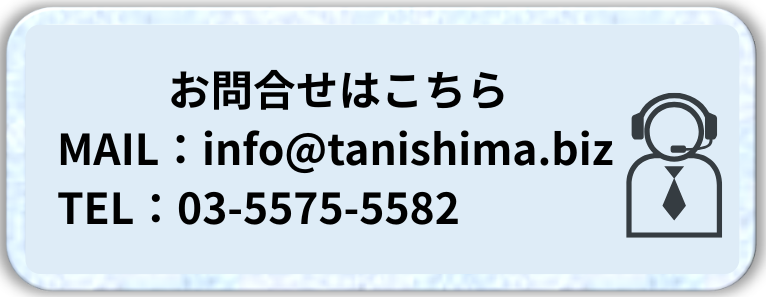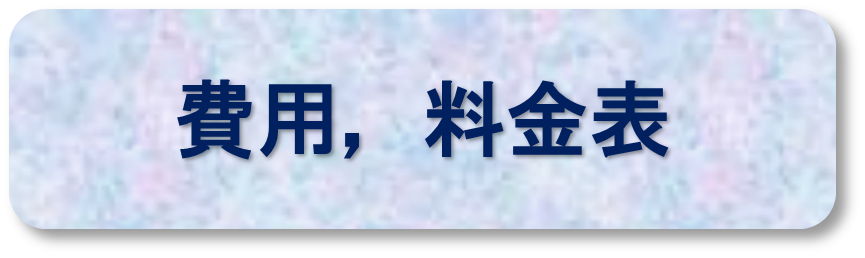内容
機械器具設置工事業で指導監督的実務経験の監理技術者資格者証交付申請
監理技術者資格者証の交付要件:実務経験可能な指定建設業(7業種)以外の22業種
必要資格・実務経験要件:
監理技術者資格者証を取得するには、原則として「一級国家資格等」の保有または指導監督的実務経験及び実務経験が必要です。
特に、建設業許可上の指定7業種(土木、建築、電気、管、造園、鋼構造物、舗装)では一級資格者等でなければ監理技術者になれません。
一方、「機械器具設置工事業」は指定業種ではないため、所定の実務経験を満たせば一級資格者がいなくても監理技術者資格者証の交付申請が可能です。以下に、一級資格等による要件と実務経験による要件を整理します。
- 一級国家資格等による要件: 監理技術者の資格要件として認められる一級国家資格には、施工管理技士(一級土木・建築・電気・管工事施工管理技士など)や一級建築士、技術士(該当分野)などがあります (資格要件 | 一般財団法人 建設業技術者センター)。これらの一級国家資格を保有していれば、基本的にその資格をもとに新規申請が可能です(初回取得や有効期限切れ再取得の場合に該当。
- 一級資格者であれば追加の実務経験期間は不要ですが、監理技術者講習の修了は別途必要になります(講習については後述)。
- 実務経験による要件: 一級資格がなくても、機械器具設置工事業のような指定外業種では一定の実務経験を積むことで監理技術者資格者証を取得可能です。一般的な基準として「10年以上の実務経験」かつ「その内、2年以上の指導監督的実務経験」が必要になります。
- ただし、申請者の学歴や保有資格に応じて必要経験年数は短縮される場合があります。
交付申請手続きの流れと必要書類
- 申請方法の選択: 監理技術者資格者証の申請はインターネット申請と書面申請の2通りがあります。
オンライン申請の場合、専用サイトから必要事項を入力し、必要書類の画像データを添付して送信、クレジットカード等で手数料を支払います。
書面申請の場合は、所定の申請書類一式を入手し必要事項を記入の上、証明書類を添えて最寄りの支部へ郵送または持参します。
以下、一般的な申請手続きの流れと必要資料について説明します。
- 申請区分の確認: まず、自身が行う申請が「新規」か「追加」かを確認します。
- 新規申請は初めて資格者証を取得する場合(※有効期限切れで再取得する場合も新規扱い)に該当します。
- 追加申請は、既に有効な資格者証を持っている方が、別の資格や別業種の監理技術者資格を追加取得する場合に行います。機械器具設置工事業の企業で1級資格者がいないケースでは、通常は該当者の新規申請(実務経験)からスタートし、その後必要に応じて追加申請(実務経験)を行う流れになります。
- 申請書類の入手: 書面申請の場合、申請書類一式を入手します。入手方法はホームページからダウンロード可能です。
- 必要書類の準備: 次に、申請に必要な書類を揃えます。機械器具設置工事業における実務経験での申請を想定した主な必要資料は以下のとおりです。
➀資格要件を証明する書類: 該当者が学歴短縮要件や国家資格等を利用する場合、その証明書類(卒業証明書や学科の履修証明、資格の合格証明書など)を用意します。例えば指定学科卒業による経験年数短縮を主張するなら卒業証明書と成績証明書(指定学科履修確認のため)が必要です。2級施工管理技士や技能士資格を保有している場合はその合格証明書コピーを添付します。
➁実務経験証明書類: 所定様式の「監理技術者実務経験証明書」に、申請業種に関する実務経験の詳細を記入します。経験した工事名、工期、工事内容、本人の職務(役職)などを記載し、2年以上の指導監督的経験があることを明示します。また、令和3年10月以降の新基準では、この実務経験の記載内容を裏付ける客観的資料の添付が必須となりました。
具体的には、指導監督的立場で携わった工事を証明する契約書、施工体制台帳、工事経歴(コリンズ情報)などの写しを添付し、当時の上司など第三者の連絡先も記載する形に改められています。これにより実務経験の信憑性を厳格に確認する運用になっています。
➂申請者本人の顔写真(縦4.5cm×横3.5cm程度・6か月以内に撮影・無帽無背景)1葉: 申請書所定欄に貼付します。インターネット申請の場合は画像データをアップロードします。
➃交付手数料の払込証明: 手数料は非課税7,600円で、書面申請の場合は郵便局の払込取扱票で納付します。インターネット申請の場合はオンライン決済で支払いが完結するため領収書の提出は不要です。
6.申請書への記入と提出: 準備した書類を基に申請書類一式を作成します。書類が整ったら、インターネットで送信するか支部等へ提出(郵送または持参)します。
➀インターネット申請の場合、専用サイト上でフォーム入力と書類データのアップロードを行い、そのまま手数料支払いまで完了させます。オンライン申請では書類不備が少なく済み、標準的に10日程度で交付処理が完了します。
➁書面申請の場合、作成済みの申請書類一式を支部窓口に提出するか、郵送します。
➂提出後、センターで書類審査が行われ、不備や照会事項がなければ受理されます。書面申請は処理に20~30日程度要するのが目安です(2~5月の繁忙期や年末年始はさらに日数を要する場合あり)。
7.資格者証の交付: 申請が受理・承認されると、一般財団法人建設業技術者センターから監理技術者資格者証(カード)が交付されます。
新規申請と追加申請の違い・共通点
- 新規申請(初回取得): 監理技術者資格者証の新規申請とは、初めて資格者証を取得する場合や、以前持っていた資格者証が有効期限切れになり再取得する場合を指します。
新規申請では、上記の交付要件を満たしていることを証明する書類(一級資格証明や実務経験証明)を提出し、審査を経て資格者証が発行されます。初回取得の場合、資格者証の交付を受けるまで監理技術者として現場に配置できないため、余裕をもって申請することが重要です。
実務経験による新規申請では審査に時間がかかるため約1ヶ月程度を見込みます。
一方、一級資格等による新規申請は審査が比較的迅速で、オンラインなら10日前後で交付される場合もあります。
- 追加申請(資格の追加取得): 追加申請は、現在有効な資格者証を保有している方が、新たに別種の資格を追加する場合に行います。例えば、機械器具設置工事業で実務経験により資格者証を取得後、さらに他の業種の監理技術者資格(例:電気工事業など)を実務経験で追加取得するケースや、新たに関連する一級資格を取得したのでそれを追加登録するケースが該当します。
追加申請が承認されると、既存資格と追加資格の両方が記載された新しい資格者証が交付されます(有効期限は元の資格者証の期限を引き継ぎます)。追加申請時は現在の資格者証情報を申請書に記載し、追加分の資格証明書や実務経験証明書を提出します。新規と同様にオンライン申請が可能で、実務経験による追加も2021年10月より電子申請対応となっています。処理期間は新規と同程度で、おおむね30日以内です。
- 共通点と留意事項: 新規・追加いずれの申請区分でも、基本的な申請手順(書類準備~審査)や必要書類の種類、手数料(7,600円)に違いはありません。どちらの場合も、交付された資格者証の有効期限は5年間であり、期限が切れる前に更新申請が必要となります。
なお、有効期限が迫っている時期に資格の追加取得を希望する場合は注意が必要です。有効期限まで6ヶ月を切って更新対象期間に入っている場合でも、同時に別資格の追加を行うときは「更新申請」ではなく「追加申請」として手続きを行う必要があります。その際、更新と追加を一緒に済ませたいところですが、一度追加申請で新しい資格者証を受け取ってから改めて更新手続きを行う形となるため、スケジュールに余裕を持って対応することが望まれます。逆に資格者証の有効期限が過ぎてしまった場合、追加ではなく新規申請扱いとなりますので注意が必要です。
交付後の注意事項(監理技術者講習の受講要件など)
- 監理技術者講習の必要性: 監理技術者として現場に配置されるためには、資格者証の携行に加えて監理技術者講習の修了が法的に義務付けられています。したがって、資格者証を取得しただけでは不十分で、実際に特定建設工事の現場で監理技術者になるには国土交通大臣登録の講習を受講し修了する必要があります。
講習の受講履歴がない場合、たとえ資格者証を持っていても監理技術者として現場に立てない点に注意が必要です。
- 講習受講のタイミング: 2004年(平成16年)以前は資格者証の交付要件として講習修了が含まれていましたが、平成16年3月以降この要件は撤廃されました。現在は講習未修了でも資格者証自体は取得可能です。従って、例えば機械器具設置工事業の社員が急ぎ資格者証を取得する場合、まず申請を行い交付を受けてから、その後適宜講習を受けるという段取りが可能です。
ただし前述の通り、専任現場で監理技術者として職務に就く前に必ず講習を修了しておく必要があります。資格者証取得と講習受講はどちらを先に行っても構いませんが、現場配置時点で両方が有効な状態であることが求められます。
- 講習の概要: 監理技術者講習は、国土交通大臣の登録を受けた民間機関等が全国各地で随時実施しています。一般財団法人全国建設研修センター、一般財団法人建設業振興基金、日建学院など計6機関ほどが登録講習機関として開催しています。
講習では最新の法令改正や施工管理の留意事項などについて学び、修了者には「監理技術者講習修了証明」(修了ラベル)が交付されます。このラベルは資格者証の裏面に貼付(または資格者証に印字)され、講習修了年月日と修了機関が記載されます。講習修了の有効期間は5年間で、修了日から起算して5年後の年末まで有効と定められています。従って、監理技術者として継続して現場配置される場合は5年ごとに再度講習を受講し、修了履歴を更新していく必要があります。なお、講習の申込みや日程については各実施機関のホームページで確認でき、監理技術者資格者証の更新案内とは別に各自で管理する必要があります。
- 都道府県特有の運用: 監理技術者資格者証の制度・申請要件は国土交通省所管の全国統一基準であり、各県独自の追加要件やローカルルールは基本的にありません。
参考資料(出典)
- 一般財団法人 建設業技術者センター「監理技術者について」 (資格要件 | 一般財団法人 建設業技術者センター) (よくある質問(Q&A) | 一般財団法人 建設業技術者センター)ほか
- 同センター「実務経験による監理技術者の資格要件」 (実務経験による監理技術者の資格要件 | 一般財団法人 建設業技術者センター) (実務経験による監理技術者の資格要件 | 一般財団法人 建設業技術者センター) (実務経験による監理技術者の資格要件 | 一般財団法人 建設業技術者センター)
- 同センター「申請手続き」 (新規申請(一級国家資格等) | 一般財団法人 建設業技術者センター) (新規申請(一級国家資格等) | 一般財団法人 建設業技術者センター) (追加申請(実務経験) | 一般財団法人 建設業技術者センター)
- 同センター「よくある質問(Q&A)」 (よくある質問(Q&A) | 一般財団法人 建設業技術者センター) (監理技術者について | 一般財団法人 建設業技術者センター) (よくある質問(Q&A) | 一般財団法人 建設業技術者センター)
- 国土交通省「監理技術者講習の実施機関一覧」 (よくある質問(Q&A) | 一般財団法人 建設業技術者センター)(講習実施機関に関する情報)
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
▶ 行政対応・顧問
▶ 外国籍人材紹介
▶ 外国人登録支援機関業務
▶TAKUMI人事
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】
コラム一覧2026年2月20日営業所(専任)技術者の退職は、変更届か取消し処分か【事例】 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは