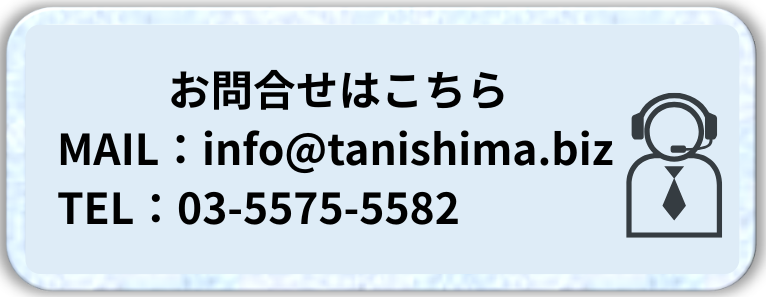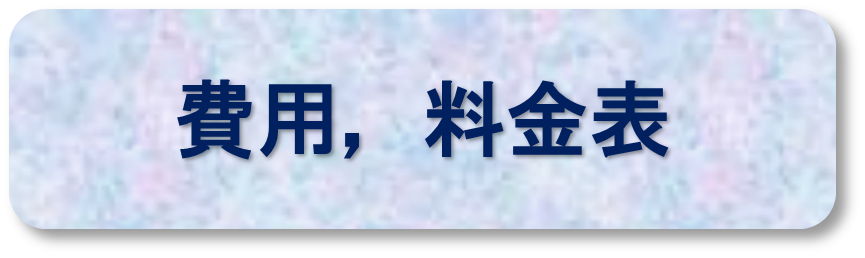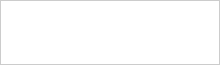Q.現場の配置技術者を専任にできない工事は建設業法違反か?
他の配置技術者との兼任が認められない専任現場とは
用途面:監理技術者の専任現場(主任技術者を含む)
請負金額面:監理技術者等の専任現場(主任技術者を含む)
下請の主任技術者は専任現場とは?元請以外も注意
他の配置技術者と兼務できる例外
片付けや先行工事の場合
監理技術者補佐を配置できる例外
Q. 現場の配置技術者を専任にできない工事は建設業法違反か?
(用途は太陽光発電設備(いわゆるメガソーラー)設置工事の場合)
※この解説ページは、コンプライアンス顧問として行政書士が建設業者である顧客への適切な回答をロールプレイング形式で行うものです。
| 1. 主任技術者または監理技術者を配置する必要がある工事について専任となるかどうかは、現場ごとに工事規模その他要素によって決まる。 |
| 2. どのような金額でも太陽光発電設備工事は常に専任を要するため、専任できなければ許可取得は無意味。 |
| 3. 工事規模にかかわらず、下請に出すと専任現場にはならないので、問題なく進められる。 |
| 4. 一度「専任を要する工事」と判断された場合、兼務は一切不可で工事中断もやむを得ない。 |
| 5. 妥当な肢は無い |
他の配置技術者との兼任が認められない専任現場とは
一定の工事現場では配置技術者が専任でなければならないとされております。つまり、すべてではありません。
主に、専任現場となる基準は、用途および金額によって決定します。
| ◆専任が必要な⼯事とは:
請負金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の個人住宅・長屋を除くほとんどの⼯事 |
出典:国土交通省、https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0501/R0501_05.pdf
用途面:監理技術者の専任現場(主任技術者を含む)
まず用途の観点で以下の通りです。
| 公共性のある施設若しくは工作物⼜は多数の者が利⽤する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事とは
①国⼜は地方公共団体が注文者である施設⼜は⼯作物に関する建設⼯事 ②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設、上下水道、消防施設、電気施設、ガス施設、学校、図書館、美術館、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、公衆浴場、教会、⼯場等の建設⼯事(個人住宅・長屋を除くほとんどの施設が対象) |
出典:国土交通省、https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0501/R0501_05.pdf
住宅であっても共同住宅なら専任が必要とされます。
つまり、片廊下のアパートは専任必要な用途です。
一方で、タウンハウスの場合は専任不要ができることとなります。長屋建の集合住宅は共同住宅ではないからです。
請負金額面:監理技術者等の専任現場(主任技術者を含む)
次に、専任現場となる「重要な建設工事で政令で定めるもの」とは金額面の規定があります。専任の配置技術者となるかは、金額の観点となります。
| 公共性のある施設若しくは⼯作物⼜は多数の者が利⽤する施設若しくは⼯作物に関する重要な建設⼯事で、⼯事⼀件の請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものについては、⼯事の安全かつ適正な施⼯を確保するために、設置される主任技術者⼜は監理技術者は、⼯事現場ごとに専任の者でなければなりません。(下請⼯事であっても適⽤されます。)(建設業法第26条参照) |
出典:国土交通省、(ただし、旧金額:4,000万円(建築⼀式⼯事の場合は8,000万円)の記載は、2025年3月現在異なります)https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0501/R0501_05.pdf
下請の主任技術者は専任現場とは?元請以外も注意
下請金額でない点で、元請だけが対象ではありません。監理技術者設置の義務金額と異なることの混同にご注意ください。
したがって、主任技術者も専任となることが多くあります。
他の配置技術者と兼務できる例外
それではすべての工事が上記2つの基準で専任現場とあるかというと、そうではありません。下記の通り建設業法令の例外があります。
「当該工事現場の施工体制の確保」については、特に有効です。これは連絡方法や移動時間によって、緩和があります。
片付けや先行工事の場合
片付けや先行工事の場合、専任が不要となることがあります。専任義務で常駐まで必ず必要となるわけではありません。その他の状況でも緩和される運用があります。
専任特例1号:主任技術者・監理技術者の専任配置の特例
金額、現場数、距離や下請次数の4つの要素により、兼任が可能な特例があります。具体的な金額として、兼任する各建設工事が、1億円未満(建築一式の場合は2億円未満)であれば、兼任できる工事現場の特例が使える規定があります。
但し、制度が複雑であるため、全ての要件を満たせるかの確認が必要です。
根拠法令
| 建設業法第26条
~略~ 3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。 一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者 イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。 ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。 ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 |
根拠行政文書
| (2)主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例
① 専任特例1号については、主任技術者又は監理技術者は、専任を要する工事を兼務できることとされており、適用にあたっては、以下の全ての要件に適合しなければならない。なお、専任特例1号は、下請け企業が配置する主任技術者についても適用が可能である。 1)各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること(令第二十八条)。なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。 2)建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。(規則第十七条の二第一項第一号)なお、左記の移動時間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。 3)当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。(規則第十七条の二第一項第二号)なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。 4)当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。(規則十七条の二第一項第三号) 連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能である。 連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)ことを想定している。 連絡員に必要な実務の経験として認められる内容は、法七条第二号に記載の営業所技術者(主任技術者)の実務の経験として認められる経験の考え方と同じでよい。 連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。 5)当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。(規則十七条の二第一項第四号)なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。 6)当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、規則二十八条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。なお、当該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。(規則第十七条の二第一項第五号、第二項) |
出典:監理技術者マニュアル、https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001765655.pdf
専任特例2号:監理技術者補佐も配置し、監理技術者が専任でも2現場が可能
一定の資格者であれば、監理技術者を専任現場に配置させても、監理技術者補佐を配置することで2現場が監理可能となります。
ただし、監理技術者業務を行うことを前提にしており、監理技術者はその業務を免れるわけではありません。
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】
コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】