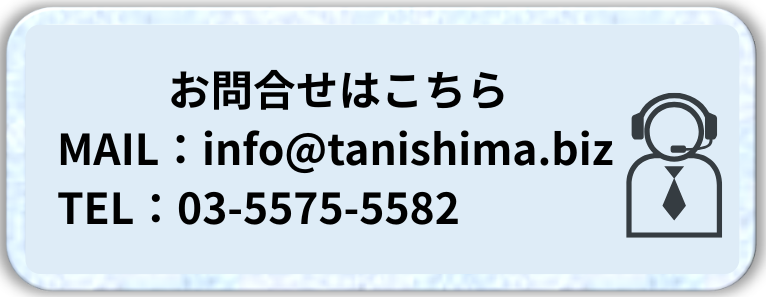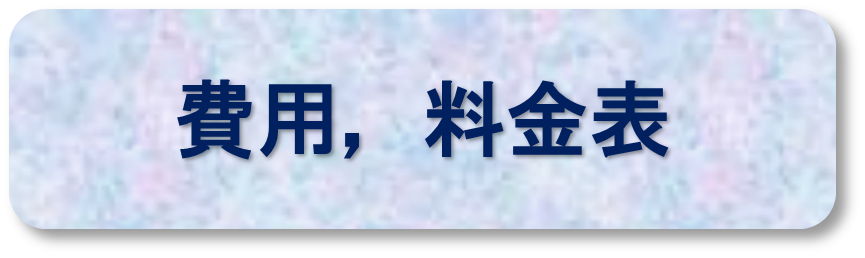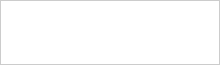Q. 建設業許可の営業所(専任)技術者は、現場の監理技術者・主任技術者になれないと聞いたが、全く不可能か?
主任技術者とは(建設業法第26条第1項)
配置技術者である監理技術者・主任技術者
営業所の専任技術者と監理技術者等の兼務は可能か?非専任現場の場合
「工事現場毎に専任する配置技術者」の専任技術者の兼任
近接の営業所でも専任技術者との兼任が認められない専任現場
Q. 建設業許可の営業所(専任)技術者は、現場の監理技術者・主任技術者になれないと聞いたが、全く不可能か?
建設業許可維持のためのコンプライアンス顧問行政書士の回答として適切なものを選んでください。
| 1. 専任技術者は、会社の常勤職員として資格要件を満たす必要があるため、監理技術者を兼ねることは一切認められない。 |
| 2. 専任技術者は、常勤かつ技術上の管理を行う立場だが、条件を満たせば主任技術者を兼務できる場合がある。 |
| 3. 専任技術者と監理技術者の業務は全く同一なので、どちらを名乗っても問題はない。 |
| 4. 専任技術者は、国家資格があれば外部委託も可能であり、実務上いつでも現場代理人を兼任できる。 |
| 5. 正解の肢は無い |
主任技術者とは(建設業法第26条第1項)
そもそも主任技術者とは何でしょうか。その答えは以下の通りです。
建設業の許可を受けたものが、その請け負った建設工事を施工するときは元請・下請、請負金額に係わらず、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を設置しなければなりません。
次に監理技術者との違いや理解が必要となります。
配置技術者である監理技術者・主任技術者
建設業許可においては、配置技術者はあまり登場しません。それは、営業所技術者である専任技術者と配置技術者である主任技術者・監理技術者という役割の違いがあります。
しかし、コンプライアンスとして建設業法で最重要です。現場に配置しない場合、違反となり、業務停止等の処分事例が多くあります。
配置技術者とは以下があります。
- 主任技術者
- 監理技術者
法令上、監理技術者か主任技術者かは金額によって変わります。
特定建設業許可相当の請負額なら、元請の場合、配置技術者は監理技術者となることが通常と思えばよいです。
根拠法令
| 建設業法第26条
(主任技術者及び監理技術者の設置等) 第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。 2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。 |
配置技術者である主任技術者と、営業所技術者である専任技術者には、違いがあります。その兼任は、原則、違反となる建設業法令の規定となっております。
営業所の専任技術者と監理技術者等の兼務は可能か?非専任現場の場合
一定の工事現場では配置技術者が専任でなければならないとされておりますが、そうでなければ、可能なのかという問いです。
この点、下記の国土交通省の文書が参考になります。
| 《注意②》「営業所における専任の技術者」は、現場の主任技術者⼜は監理技術者になることができないことに注意しよう!
「営業所における専任の技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(⼯法の検討、注文者への技術的な説明、⾒積等)を行うことが職務ですから、所属営業所に常勤(テレワーク含む)していることが原則です。例外的に、技術者の専任が求められない⼯事であって、 ①当該営業所において契約締結した建設⼯事で ②当該営業所の職務を適正に遂行できる程度近接した⼯事現場 ③当該営業所と常時連絡をとれる状態である場合には、当該⼯事現場の技術者になることができます。※①〜③の全ての要件を満たす必要があります。(監理技術者制度運⽤マニュアル二-二(5)参照) |
出典:国土交通省、https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0501/R0501_05.pdf
つまり、原則、違反となります。営業所の専任技術者は営業所毎に専任が義務付けられているからです。
ただし、例外的に可能な場合があります。それは、近接している時が可能な基準となります。
つまり、金額が低い現場であって、近接した現場なら、営業所に常駐しなければならない義務は、例外を使うことができます。
ただし、専任現場でないかどうかの金額確認が必要です。
したがって、「条件を満たせば主任技術者を兼務できる場合がある。」という回答が妥当となります。
営業所と近接する現場の基準は、現在「現場と営業所が直線距離10km以内」なら許容する運用となっております。
「工事現場毎に専任する配置技術者」の専任技術者の兼任
工事現場ごとの専任は、原則、金額と用途で決まります。
元請⼯事については、基本的には契約⼯期が専任で設置すべき期間とされます。
下請けでも専任現場が必要となることが多くあります。
上記の通り、専任現場の場合は、また回答が異なります。工事現場の専任については、別の記事で解説しております。
近接の営業所でも営業所(専任)技術者との兼任が認められない専任現場
近接する現場の場合、専任技術者の兼任が認められる場合があります。
しかし、営業所(専任)技術者の兼任の例外が使えるかどうかは、「技術者の専任が求められない⼯事であって、」という条件があります。
したがって配置技術者が専任の工事現場では、営業所の専任技術者との兼務はできないということになります。
上記の距離の例外は、そのような「専任現場」でなければ、営業所(専任)技術者の兼任が認められるということになります。実際に行政の運用もそうされております。
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
- 対応サービス
- 資格等特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
 コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否
コラム一覧2025年12月9日電気通信工事「機器売買」額の合算・分離基準は?特定建設業許可と専任技術者の要否 コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要?
コラム一覧2025年12月5日特定建設業許可の5000万円下請額は材料費別?監理技術者の配置不要? コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは
コラム一覧2025年11月1日建設リサイクル法の解体・新築事前届出とは コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】
コラム一覧2025年10月31日建設リサイクル法の届出工事【機械器具・設備の解体や撤去】